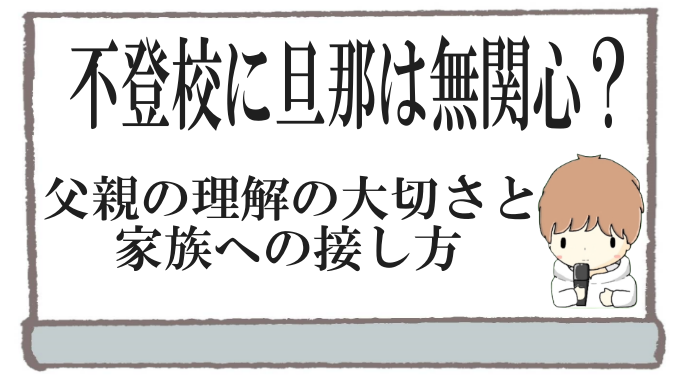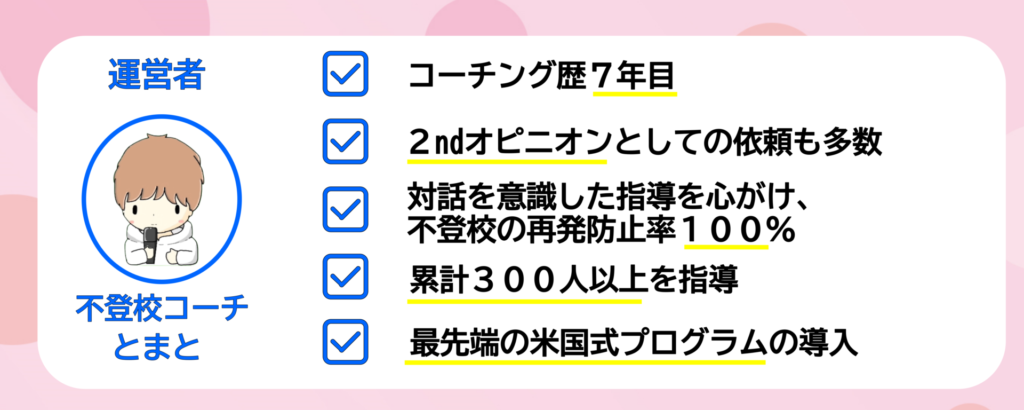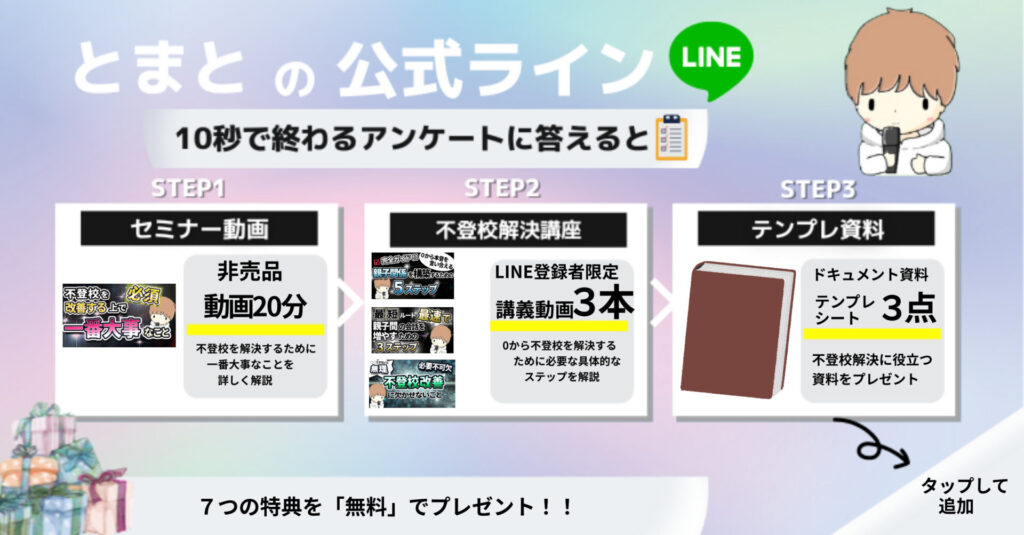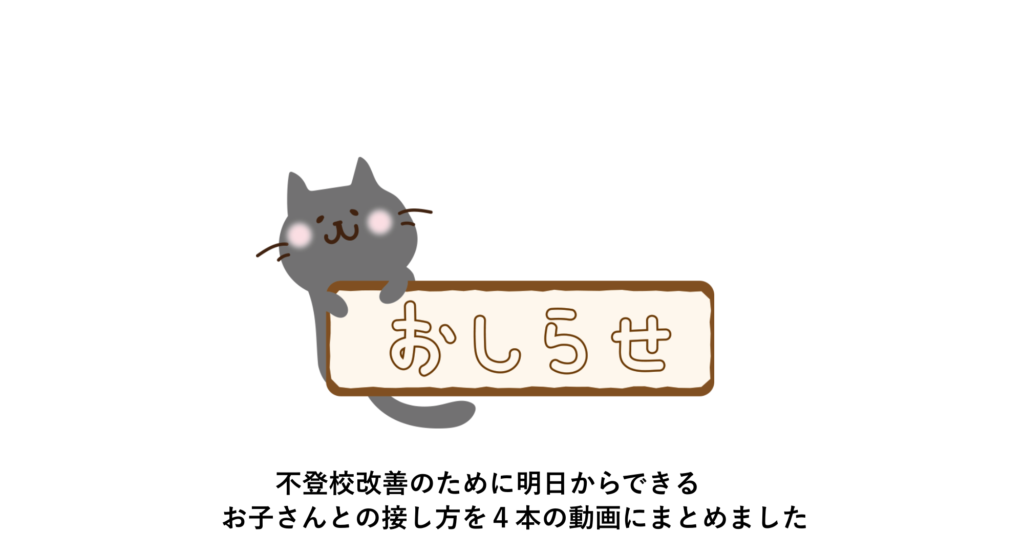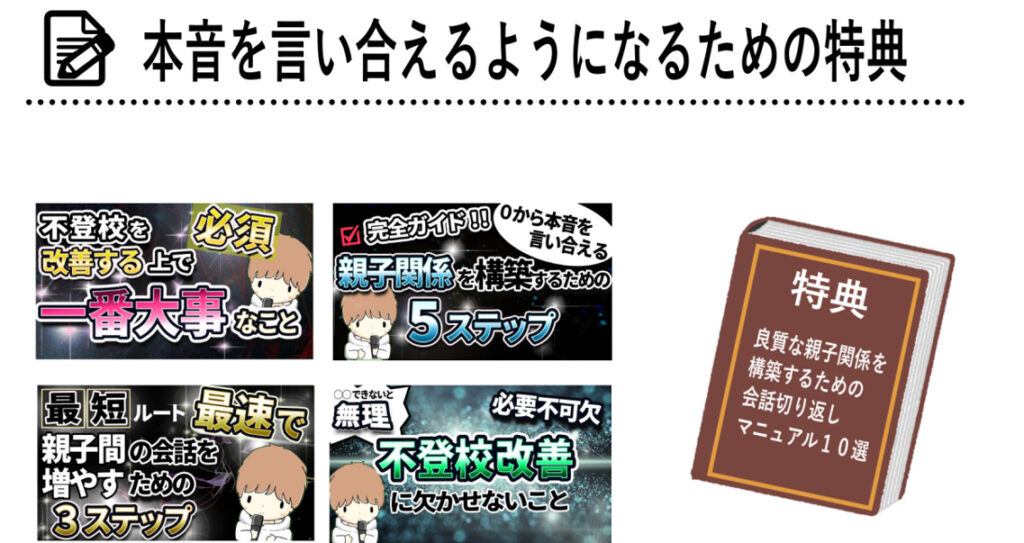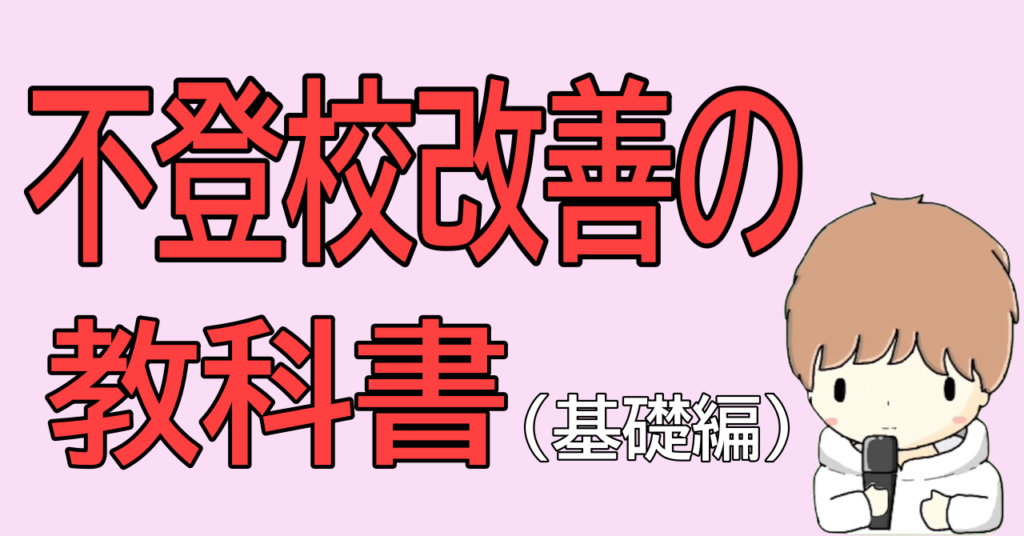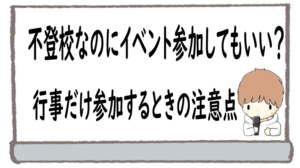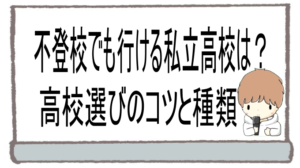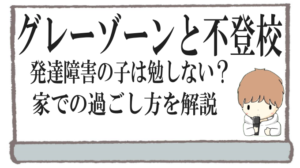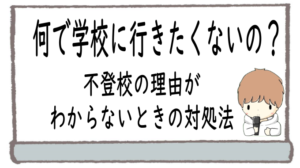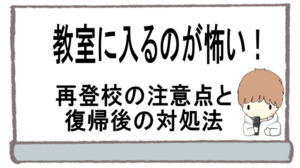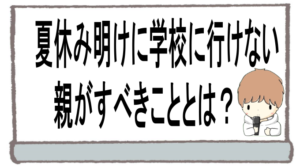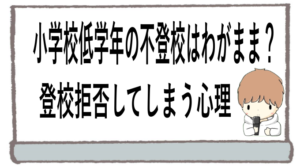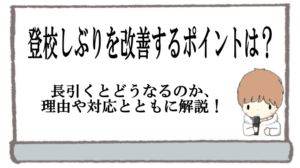子供が不登校なのに、旦那は無関心。
協力してほしいのに、子供のことは母親任せで、不登校に理解がないみたい…。
夫婦で協力しなくちゃならない時なのに…。
こんにちは、とまとです。
“イクメン”などの言葉が当たり前になっている時代ですが、やはり『子供のことは母親に任せる』スタイルのお父さんも多いのが現実です。
父親の役割は見守るだけしかないと、思っている旦那さんも少なくないのですよね。
特にお子さんが不登校になったりすると、
- 接し方がわからない
- 不登校になったことがないから理解ができない
- 母親じゃなきゃわからないこと
などと、ちょっと逃げ腰になってしまう旦那さんも少なくない、という事象も見られます。
 母親
母親母親だって不安だし、子供のことなんだから一緒に考えてほしい
という意見が多く聞かれるのも事実です。
この記事では
- 不登校に対する旦那の理解がないと感じるのはなぜか?
- 不登校のお子さんへの父親の接し方
- 不登校のお子さんのいる家庭での父親の役割
を中心に解説します。
子育てには父親の力も必要です。
特に不登校というマイナスの状況の時こそ、『父親の理解・父親の役割は大切になる』のです。
夫婦で、お子さんに向き合うためのヒントになる記事です。
子供の不登校に無関心な旦那が多いのか


『子供のことは母親が見るべき』という風潮はなくなってきたものの、やはり不登校などの緊急事態には、母親のほうが負担を多く追っていると感じる女性は少なくありません。
では、父親である旦那が『無関心』だと感じてしまうのは、どうしてなのか?どんな時なのか?
この章では、奥さんが感じる不登校のこどもへの旦那の関心について解説します。
不登校に対する父親と母親の感じ方
誰だって、不安なときはその気持ちを共有して支えあってくれるだれかが必要だと感じることが多いでしょう。
家庭の中では、お子さんの成長を一緒に見守っている夫婦はその役割を果たせる大切なパートナーです。
しかし、何となく『子供のマイナス面は母親がカバーする』というイメージが多いのも事実です。
例えば—
◎公園に行ったりゲームをしたりするのはお父さん
△勉強や生活習慣を叱るのはお母さん
◎おもちゃやお菓子を買ってくれるのはお父さん
△それを制限するのがお母さん
といったふうに、『母親って貧乏くじ引かされてるなぁ』と感じる奥さんも多いこともわかっています。
もちろん、それでもお子さんはお母さんを嫌いになったりすることは少ないです。
しかし、やはり不登校になった時母親は
- 何が原因なのか?
- 何で学校に行ってくれないのか?
- いったいなにをしてあげたらいいのか?
と考え込んだり、周りからも責められているような気持になったりする人が多いというデータもあります。
しかし、父親は少し違うようです。
- 何で学校に行きたくないのか?
- 学校に行かないなんて普通じゃない
- 甘えてるんじゃないのか
といったように、感じる人が多いというのです。



つまり、母親は子供に寄り添う目線の人が多く、父親は分析して軌道修正をさせる気持ちが働きやすいということです。
なぜ子供の不登校に旦那が無関心だと感じるのか
実際に、『そういうのは母親の役割だろ』と思っている人もいないわけではありません。
しかし、前に書いたように、不登校の我が子に対して、父親も『なぜ?』『どうして?』という疑問がわいているのは事実です。



じゃぁなんで協力してくれないの?
それはずばり、
『どうすればよいのかわからない』
ということが理由にあげられます。
実際、育児に参加している旦那さんでも、そう思うこともあるのです。
不登校のお子さんに関して—
- 奥さんに任せていたからわからない
- 何となく病気や悩み事は母親のほうが安心
- 自分は不登校になったことないから気持ちがわからない
といった意見が多く聞かれます。
特に女の子のお子さんを持つお父さんは、デリケートな問題に首を突っ込んで、こじらせるのが怖いという考えも持っていることが多いです。
もちろん、全員がそういった考えをもっているわけではありません。
お子さんと、何でも話せる良好な関係を築いていらっしゃるお父さんもいるでしょう。
しかし、多くの場合旦那さんは、『どうして?』『なんで?』を直接お子さんに聞くこともできず、悩んでいる奥さんにも話しかけられず、結果として『無関心』だと思われてしまうことが多いのです。
不登校に対して旦那の理解がない
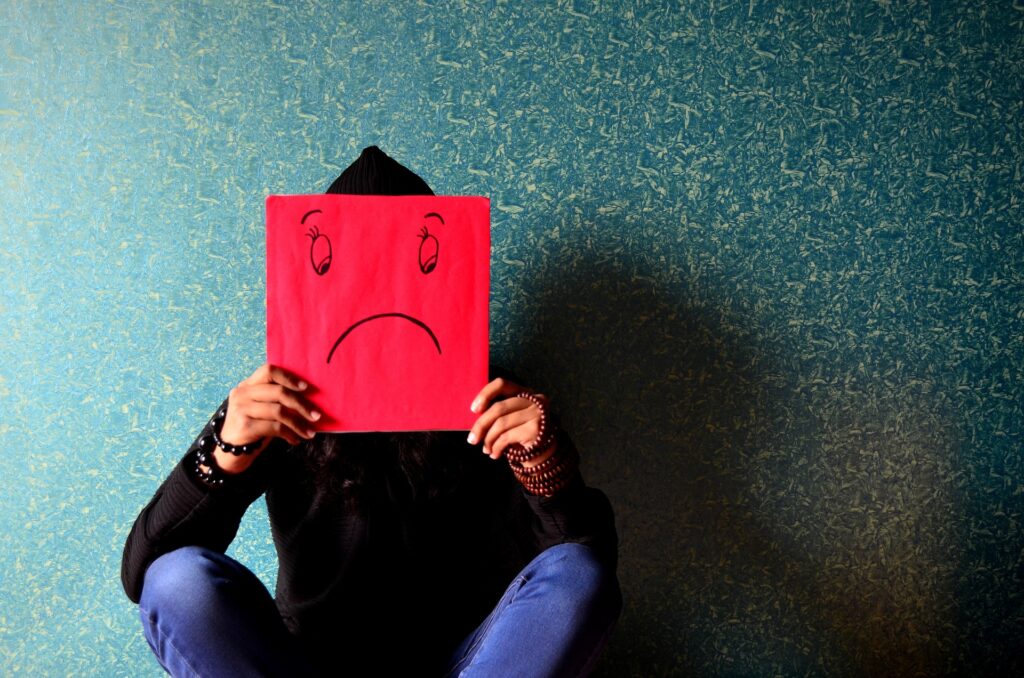
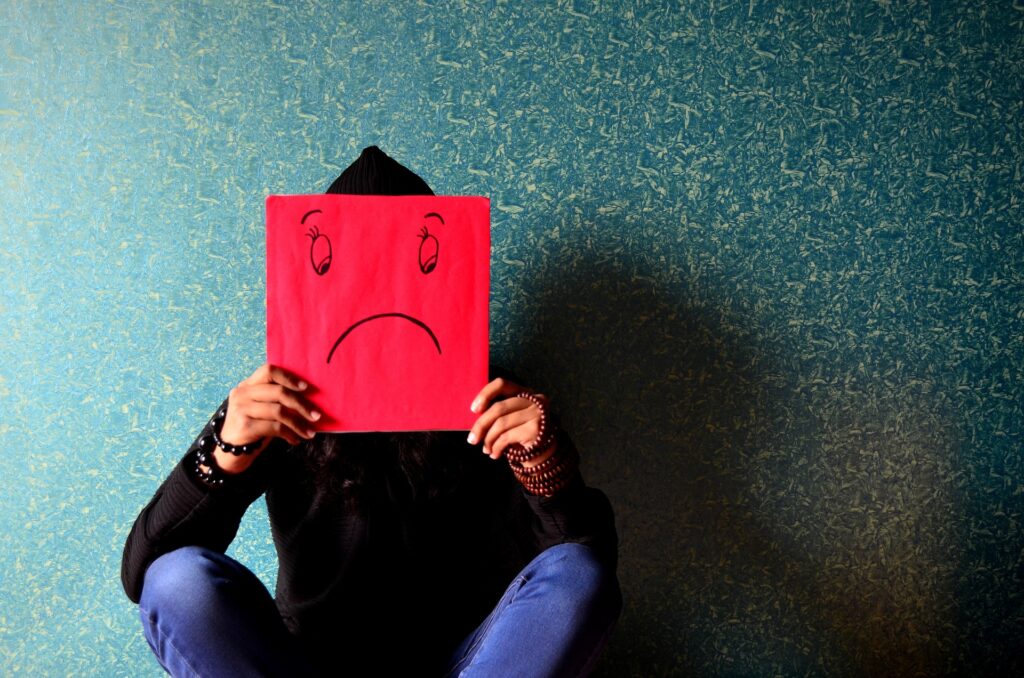
旦那さんの中には、不登校に関して理解のない人もいます。
学校に行かないことを恥ずかしいと感じたり、ありえないと感じるからです。
この章では、理解できない旦那の気持ちとその対処について解説します。
不登校のご家庭にある父親像
不登校のお子さんがいる家庭でよくあるパターンとして、
- 父親の存在が見えない
- 父親の存在が大きすぎる
ということがあります。
詳しく解説すると以下のようなことです。
父親の存在が見えない
学校や、カウンセラーさんが感じる不登校のお子さんの父親で一番多いパターンです。
要するに、『家のことは母親に任せている』というタイプの旦那さんですね。
このタイプの旦那さんがよく口にするのは
- 『育児は母親の仕事』
- 『仕事があるから』
- 『そのうち何とかなるだろ』
といった言葉です。
このタイプの父親がいる家庭では、母親は1人で全部抱え込んでしまうことが多いです。
また、お子さんにとっては『自分には興味がないんだな』という気持ちになる一言です。
父親の存在が大きすぎる
これは決して、偉大なお父さんという意味ではなく、重圧のある父親という意味です。
なんでも、上から押さえつけて、自分の意見を押し通すタイプの人が多いです。



いわゆる昭和のお父さん像といったところでしょうか
確かに、リーダーシップがあって頼りになるかもしれませんが、子供と母親は委縮してしまうことが多いです。
このタイプの父親は、お子さんの不登校に対して否定的です。
- 『絶対に休むな』
- 『学校に行かないなんて甘えだ』
- 『さぼらせるな』
このような少し強い言葉で、強引に登校させようとします。
母親にとっても子供にとっても、どんどん引きこもってしまう言葉ですね。
どちらの父親の場合でも、『学校へ行くのが普通』という考え方を持っていることが多いです。
学校に行かないことへの抵抗感が理解のなさにつながっている
前述したように、学校へ行くのが当たり前と思っている父親は、わが子が不登校であることに抵抗感を持っています。



『不登校=恥ずかしいこと』という認識なのです。
もちろん父親だけではありませんが『学校へ行くのは普通でしょ?』と思っているのは圧倒的に父親のほうが多いのも事実です。
父親の考える『普通』がうまくいかないのは
- 子供が甘えているから
- 母親が甘やかすから
- がんばりや努力が足りないから
だと思っている旦那さんも少なくありません。
その根底には、『自分に不登校の経験がない』ということがあります。
不登校に理解のない旦那さんの多くは、この経験がないというのが理由にあげられるのです。



旦那さんの子供の時は、多少いやなことがあっても学校に行っていたし、行かされていたのです。
また、『学校が楽しかったという思いでしかない』という父親も、不登校のお子さんの気持ちを理解できないことにつながってしまいます。
学校に楽しい思い出があるというのは悪いことではありません。
自分の子供にだって学校が楽しいところであって当然というのは、違うということに気づけず、学校に行くことを強要してしまうパターンも少なくありません。
どうしたら旦那が不登校に理解を示してくれるのか?
不登校に対して旦那の理解がないのは、母親にとってはつらいことです。
母親一人で抱え込んでしまうばかりでなく、旦那の意見を押し付けられては負担も大きくなってしまいます。
また、紹介したように甘やかしているなどと母親に責任を押し付けるようなことも少なくありません。



子供の不登校というだけでも大変なのに、私は誰に頼ればいいの?
夫婦なのに、子供の一大事に寄り添って協力できないというのは、悲しいですよね。
母親にとって、旦那に求めるのは『寄り添い』と『共感』ですよね。
では、旦那に理解してもらうにはどうしたらいいのか?
それにはいくつかのやり方があります。
- お子さんの状況を説明する
- 旦那の考えをしっかり聞く
- これからどうするのかを伝える
母親にとっても父親にとっても、お子さんの不登校は青天の霹靂。
特に、父親はその対処がわからないし、何からすればよいのかわからないと感じやすいと言われています。
否めないことですが、お子さんのことに関しては、母親のほうが適応する能力があることが多いです。



つまり、主導権を母親が持つことが、夫婦でお子さんに向き合うポイントであるといえます。
それでもやっぱり、理解してもらうことが難しい、という方もいらっしゃるでしょう。
その時の重要なのはこれ!
『子供のことは、母親である自分にまかせてもらう』
理解してもらおう、協力して解決しよう、と思うとそれが余計なプレッシャーになることも多いのです。
とても勇気のいることですが、不登校なのはお子さんで、それで悩んでいるのはお子さんなのです。
お子さんの気持ちを最優先で考えましょう。



母親はどんな時でも味方になってくれるというのは、お子さんには心強いことです。
理解してもらえなくても、ぶれないスタンスを持つことが大切です。
そして、母親のぶれない姿勢は、旦那さんをはじめ周りの気持ちも変えることができるという結果も多数あります。
不登校のお子さんへの父親の接し方


不登校のお子さんに、父親はお子さんとどう接したらよいのか?
理解しがたい状況の中で、その接し方はとても難しいでしょう。
この章では、不登校のお子さんに対する父親の接し方を解説していきます。
ここからは、お父さんに向けてもお話ししていきますよ。
父親が不登校のこどもや家族にしてしまいがちなこと
繰り返しになりますが、大半の父親は、子供が不登校になった時どう接していいかわからないのが現実です。
特に父親が気にしてしまうのは『世間体』です。
わが子が学校に行かないことにも、そのために会社を休んだりして、周りに迷惑をかける事にも引け目を感じがちです。
よくやってしまうのは
- 無理やり学校に行かせようとする
- 学校に行かないことを責める
- 母親のことも責める
ということです。
逆に『学校なんて行くの当たり前なんだから、ほっといたらそのうち行くだろう』と、まったく家庭に目を向けないというパターンも少なくはありません。
どちらの場合も、親の会やカウンセリングにへの参加は消極的になってしまいます。
不登校の子供を持つ家族と父親はどのように接したらよいのか
不登校のお子さんは、心も不安定で家族との距離感は難しいものです。
ではどうしたらよいのでしょうか?
大事なのは、以下のことです。
- 子供が話したらまずは3秒黙って聞く
- 母親の気持ちや情報を聞く
- 原因を究明したリ、学校の話ばかりしない
不登校のお子さんは、自分の気持ちをまとめることも困難であることが多いです。
せかさないで、ゆっくり話を聞く姿勢を持ちましょう。
つまり、お子さんに対しても奥さんに対しても、『受け入れる』と『寄り添う』というのが接し方のポイントになります。



お子さんは、親のことを見ていないようでしっかり感じ取っているのです。
接し方がわからなくても、夫婦で連携をとるだけでも、家族にゆとりが生まれます。
子供に接するときも奥さんに接するときも、聞く姿勢でいるということが大切なのです。
家庭の中に不登校の原因があるという事例は実はとても多いんです。
お子さんは親の子と家族のこと、親が思うよりも敏感に感じ取っています。
こちらの記事で、子供が不登校になりやすい家庭やその問題をチェックすることで、接し方のポイントの参考にすることができますよ。
不登校になりやすい家庭の特徴 不登校になる子、ならない子の違いとは?
不登校の子供がいる家庭の父親の役割


子供のことは母親の仕事、と思っている旦那も多いと書きましたが、それで大丈夫でしょうか?
子供にとっては、家庭の環境も不登校につながる要因のひとつです。
この章では、不登校のお子さんを持つ家庭における父親の役割について解説します。
子供の不登校は母親だけの問題ではない
ここまで、紹介したように、イクメンという言葉が生まれた今でも、病気や不登校などのお子さんの問題は、母親だけが向き合っているという現実もまだまだあるのです。
繰り返しになりますが、学校に相談に行ったり、カウンセリングや親の会にも『母親だけが行けばよい』という父親のほうが多いです。



それだと、子供と母親の一対一の狭い世界になってしまいます。
共働きの親御さんの場合には、母親が仕事を辞めるかどうか悩んでしまう場合もあります。
母親の負担や気持ちを知っておくことは不登校の子供がいる家庭では、重要なポイントです。
こちらの記事で、そんな母親の負担について紹介しています。
共感の第一歩になる、参考にどうぞ。
子どもが不登校で親も限界・つらい…仕事をやめて見てあげた方がいいの?と疲れた方へ
お子さんから見ても、『お母さんは自分のために頑張ってくれている』とは感じるものの、『お父さんは?』となってしまいます。
確かにずっと両親で子供につきっきりというのも、子供にとっては重荷になることもあります。
しかし、『見守る』というのと『放っておく』というのは同じような距離感でも、全然違うものなのです。



お子さんは、父親が無関心なのか気にかけてくれているのかをしっかりかんじとっているものなのです。
では、父親の役割とは何なのか?
それはずばり、『受け皿になる』ことでしょう。
つまりどういうことなのか?解説します。
不登校の子供を持つ家庭での父親の役割とは?
やることがわからなくても、自分の子供のことは心配なのは父親も母親も同じこと。
家庭で大事なのは、夫婦の足並みをそろえることです。
そのために、父親が負うべき役割は、以下のようなことです。
- 登校や学校に関してお子さんに過度な干渉はしない
- 母親と子供の関係を見守る
- 子供だけでなく母親の話も聞く
不登校のお子様がいる場合、家庭での父親の役割は子供と向き合うことだけでなく、
『母親にも寄り添って共感すること』なのです。
親の会や、カウンセリングにも積極的に参加して、子供の状況を知っておくことも大切です。
そうすることで、いざという時、お子さんも奥さんも支えることができるからです。



普段は、母親に対応を任せておいてもよいのです。
むしろ、母親にかじを取ってもらったほうが、うまくいくことも多いです。
しかし、放っておくのではなく、いつでもサポートできる状態でいる事を忘れないでください。



旦那にわかってもらえるのは一番心強いわ



お子さんにとっても母親にとっても、父親が理解者であるというのは大事なことなのです。
不登校の子に旦那は無関心?理解がない?父親の役割と家族への接し方を解説 まとめ


この記事では、不登校の子供を持つ家庭の父親について、母親・父親の両者に向けて解説してきました。
不登校というお子さんの難問に対して、夫婦の協力は大変重要なことであるとおわかりいただけたでしょう。
父親が無関心というわけにはいかない問題なのです。
この記事のまとめ
- 不登校のお子さんに旦那が無関心だと感じている母親も多い
- 不登校に対して旦那の理解がないのは『経験がない』という理由も多い
- 父親が不登校に理解がない時は母親が主導権を持つのも一つの手段
- 不登校のお子さんがいる家庭の父親の役割は『サポート』である
不登校が理解できない、どういう接し方をしたらいいのかわからないという父親も、子供の状況を母親と共有することで、サポートという役割があると、無関心でなくなることも多々あります。
旦那の理解がないことで、母親と子供にとっても追いつめられやすくなってしまうことも少なくありません。
まずは、『不登校=恥ずかしい』ことでないこと。そこから始めていきましょう。
旦那が共感してくれることで、家族全体の空気も変わってきますよ。
この記事を読んでいただいたら、まずは夫婦で同じ方向を向いて、不登校のお子さんに寄り添っていきましょう。
最後まで読んでいただいてありがとうございます。
こちらもどうぞ。