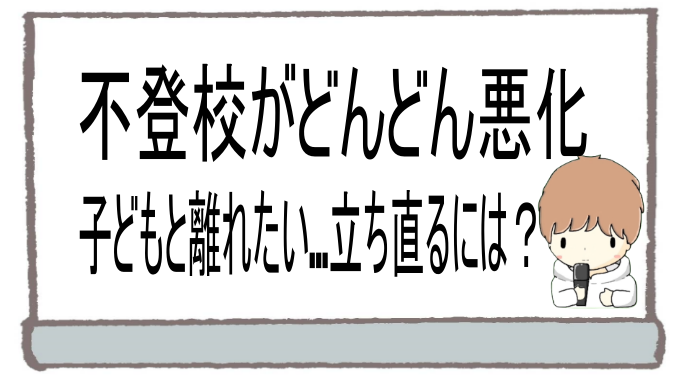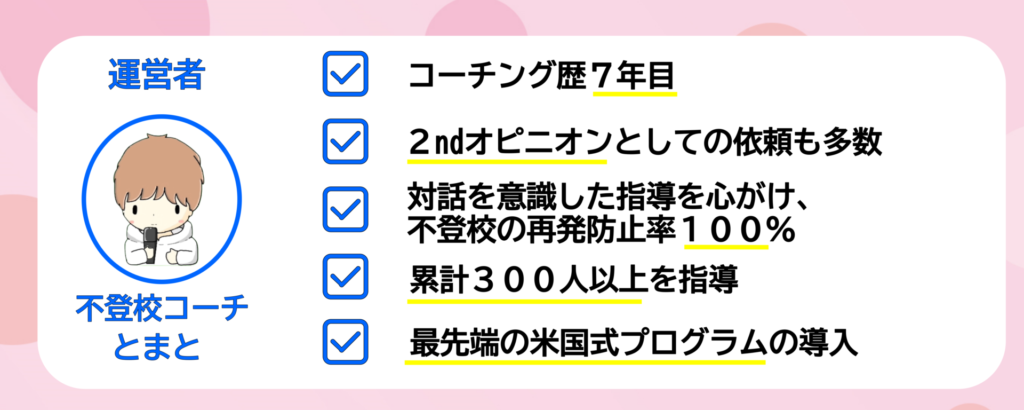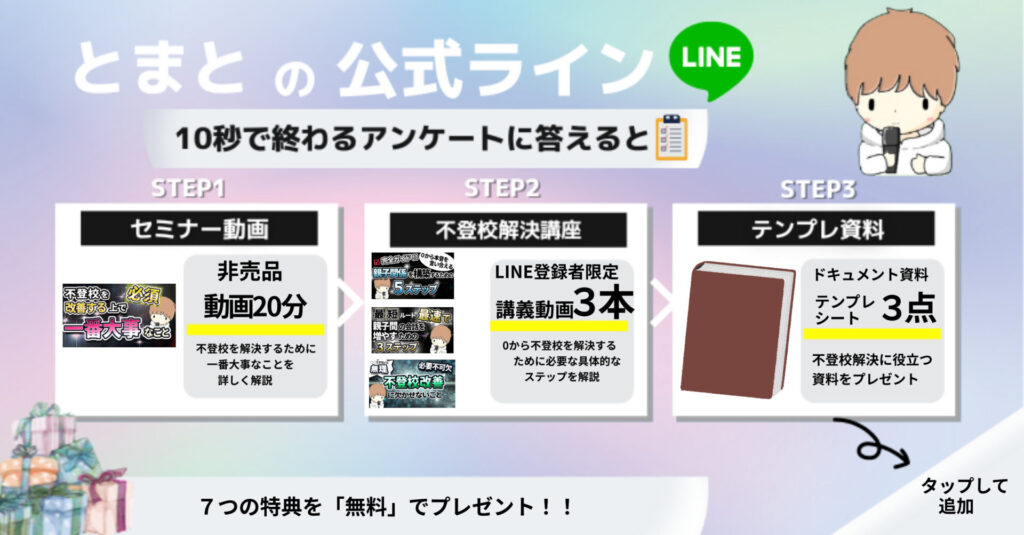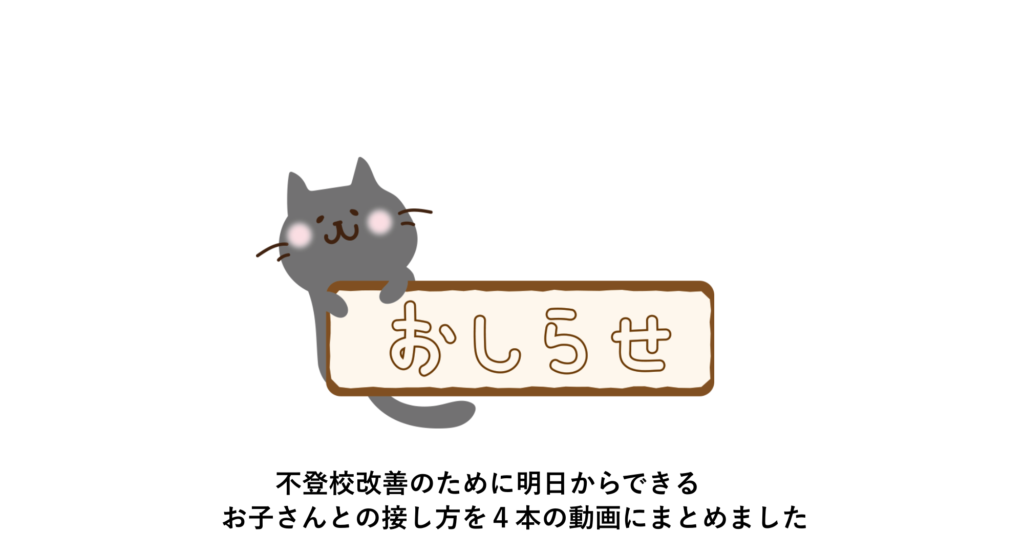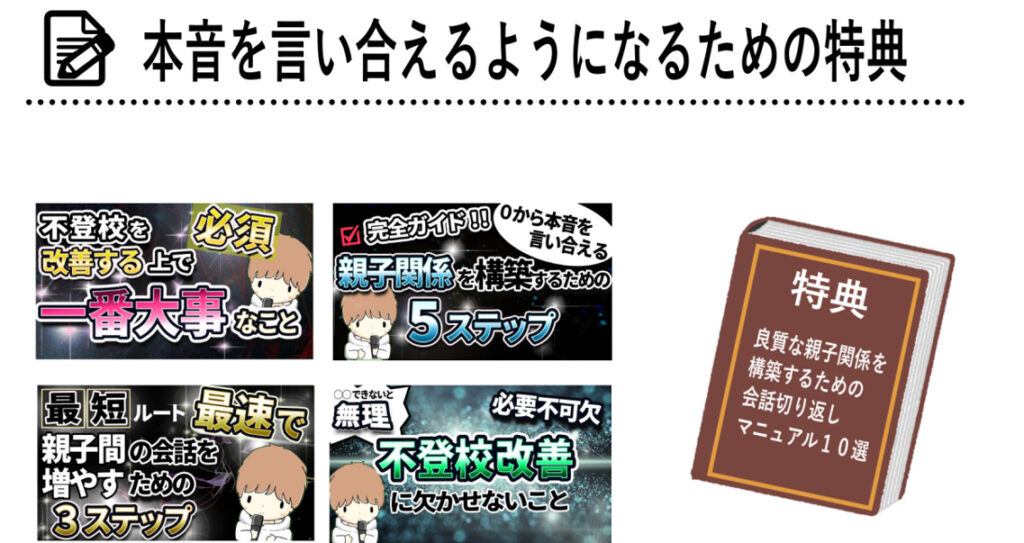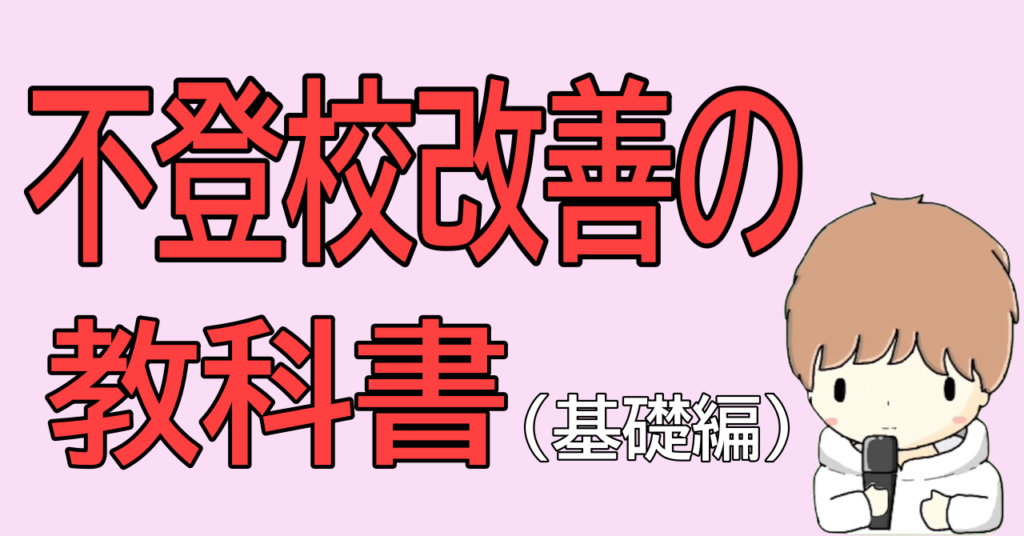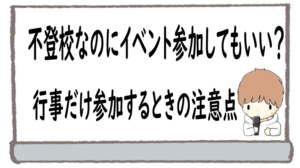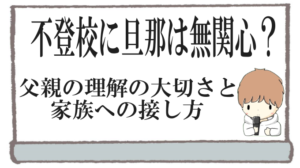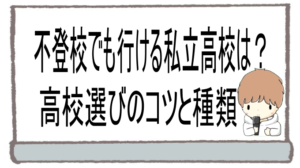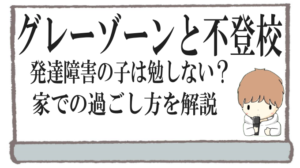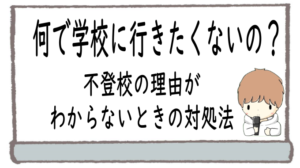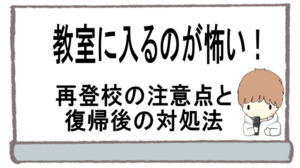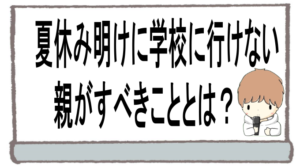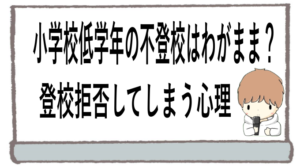こんにちは、とまとです。
子どもの不登校がどんどんひどくなる…立ち直るきっかけは?
不登校でずっと家で過ごしているけれど、苦しくて子どもと離れたい
不登校のお子さんがいる親の悩みとして、不登校がどんどんひどくなることや、子どもとずっと過ごすことで
親御さん自身がしんどくなってしまうということがありますよね。
 母親
母親できることなら早く解決して学校に行けるようになってほしい



けれど、どうしたらいいのかわからない
本日は、このようにお子さんのことについて真剣にお悩みな親御さん方への対処法を順番に解説していきます。
不登校がどんどんひどくなるケースと対処法


子どもの様子を近くで見ていて、どんどん不登校・ひきこもりの状態がひどくなっていくと不安ですよね。
昼夜逆転で取り戻せなくなってしまうのではないか等、不登校に関する漠然とした悩みも多いかと思います。
学校に行く間隔が伸びて、子どもの自尊心が失われていく
不登校には3つの時期があり、不登校がどんどんひどくなるケースは基本的に不安定期と停滞期が多いです。
- 不安定期…不登校初期の気持ちが不安定な時期
- 膠着期…不登校から1~3週間経って、気持ちが落ち着いてきた時期。一番復学しやすい時期でもある
- 停滞期…膠着期が終わり、不登校が定着してしまうと共に、自分を責めたりして再度気持ちが不安定になる時期
不安定期の親の対応としては子どもの様子を見て、待つこともあります。
ですが、どんどんお子さんが家から出られず不登校が常態化してしまうのは、停滞期に放っておいてしまうケースです。



子どもは停滞期に不登校であることに対して不安な気持ちや、自分を責めてしまう感覚を抱えています。
それに対して、親が迷いながら一貫性のない態度を取ってしまうと、子どもは余計に混乱して悪化してしまうことがあります。



じゃあ、停滞期に放っておかない為には、まず不登校の原因を突き止めたらいいのかな?
確かに、原因がはっきりあるならそれをまず無くせばいいと考えるかもしれません。



ですが、原因が特定できたから不登校がすぐ解決できたという話は聞いたことがありますか?
不登校の原因を特定できないことによって、不登校が治らないという記事もありますが、不登校の原因はわからないことが非常に多いですよね。



うーん、ならここで親がするべき対応ってなに?



1つは、なんで学校に行けないかの原因解明に固執しないことですね。



さらに、子どもがしていいこと・悪いことの線引きは一貫して伝えながら、親子のコミュニケーションをよく取ることです。
子どもの自信や自己肯定感を心配するなら尚更、子どもとの対話をしてお子さんのいまの状態を受け入れることが重要になります。
部屋に引きこもりゲーム・YouTube・SNS依存がひどくなる
不登校になると陥りやすいのが、自室にひきこもってYouTubeばかりやゲーム三昧になることです。
不登校から復帰して、学校に行ってほしいと願う親御さんからすると頭を抱える状況ですよね。



このように不安に思うのも無理はありません。



ゲームができるなら学校にも行けるでしょう!



YouTube・SNS依存になってこのまま就職もできずにひきこもりが続いたらどうしようか…



ただ、この場合よく注意して考えて頂きたいのが、不登校の直接の原因はゲーム・YouTube自体ではないかもしれないということです。
ついつい子どもの行動自体に目がいきがちですが、不登校であることに対する葛藤を和らげたいという背景があったりもします。
そこを親目線で見てなんで学校に行けないのかわからず問い詰めたりしてしまうと解決が難しくなります。
その場合にゲームを取り上げるか、改善の為に親ができることは何かについてはこちらで詳しく解説しているので、確認してみてください。
▼ こちらもチェック ▼
部屋にこもって出てこない、三度の食事よりゲームというお子さんにどう対応すればいいのか
家では元気で普通に過ごせる
不登校でどんどんひどくなるケースの中でも、「子どもが家にいる間は元気なんです」という親の声も多数あります。
朝学校にみんなが登校する時間になると、体調不良を訴えて布団から動けないけれど、
日中家にいる間は案外普通に動いて、買い物や友人と遊ぶことはできるというお子さんもいます。



子どもが甘えているだけなのでは…厳しくしないといけない



親からすると一見甘えだと思って厳しくしてしまいがちですが、逆効果です。
こちらは、膠着期に起こりやすく、学校復帰に繋げやすいタイミングとも言えますが、この状態で、無理に学校にいかせても親子関係がこじれてしまうこともあるのです。
家で元気に過ごせている場合、特に以下の2点を意識して接してみてください。
- 学校に行かないと社会で通用しないという固定観念を捨てる
- 不登校の原因の特定より、不登校を受け入れることを重視
子どもが家では元気なのに学校に行かせず、親として失格なのではないかなどと悩む時もありますよね。
ですが、これは回復するまでに必要な期間なので、親御さん自身も自分を責めなくて大丈夫なのです。
不登校の子の親に見られる4つの傾向


そもそも前提として、不登校は「親の育て方」とは直接的には関係しません。



不登校はどのような家庭のお子さんであっても、いつでもなり得る可能性があります。
それを踏まえたうえで、不登校子どもをもつ親御さん同士でもし共通点があるのなら、
どんな部分か知りたいという方の為に書いていますので、ぜひご活用ください。
傾向①親自身に不登校の経験がない
一つに、親自身に登校拒否の経験がないという傾向が言われることもあります。
子ども自身様々な要因で不登校になることがありますが、親に不登校の経験がない場合、こういった所を
理解することが難しくはなります。



他の記事ではそれによって、不登校に結びついているように記載されているものもありますが、親の不登校経験の有無で子どもが不登校になったと聞いたことがありますか?



いや、さすがに関係ないんじゃないか?
例え親御さんに過去に不登校の経験があったとしても、子どもと状況や時代が異なりますし、全てを把握できるわけではないです。



どうして子どもが不登校であるのか



不登校の対応をどうしたらベストなのか
確かに不登校について元々身近なものではない場合、決して全ての人が当てはまるわけではないですが、



その過程や心境の変化に気づくことが容易ではなく、その結果、不登校が長引いてしまうという事態も稀にあります。
経験したことがないことによって、重たく捉えて疲れてしまう部分があったり、強い不安を感じてしまうかもしれませんが、
不登校経験の有無は子どもの不登校とはほぼ関係がないと言えるでしょう。
傾向②教育熱心
不登校の子どもの親御さんは教育熱心な方が少なくありません。
以下のような動機で熱心な方もいます。
- 親自身、勉強熱心で幼い頃から塾通い+高い学歴をもっている場合、子どもにも同等の教育を受けさせたい
- 逆に勉強では苦労してきたから子どもには同じ思いをさせたくない
どちらも子どもの将来をより良くできるように動いていて子ども想いの親御さんです。
ただ、親の期待と子どもの勉強したいという気持ちが一致しているうちはいいのですが、親の過度な期待に子どもがプレッシャーを感じて心折れてしまうケースもあります。
難関と言われる学校の受験を目指して勉強しているとストレスは大きいですが、親としてもサポートを沢山しているので、
子どもの気持ちに気づきにくくなっていることもあります。



子どもとすれ違ったり、不登校になる前の兆候に気づかないまま、どんどん進めてしまいます。



そして、不登校として体調不良や学校に行けない心の状態になってやっと発覚します。
親御さんとしても子どもを応援したい気持ちから善意でしていることなので、余計に苦しくなって、
一旦子どもと離れたいなと感じます。
傾向③子どもとのコミュニケーションが少ない
その次の傾向としては、親子でのコミュニケーションが少ないことがあります。
日頃からの親子での対話が少ない場合、自分の子どもがある日突然不登校になったように感じがちですが、
子どもとしては以前からサインを出していて、徐々に限界を迎えてきて、不登校として現れる場合があります。



コミュニケーションを取るといっても、子ども自身が話すことを拒否していたり、親だけの問題ではないことがほとんどです。
例えばこんな原因があります
・仕事で深夜まで外に出ているので、子どもとの生活時間が合わない
・子どもに話しかけたら嫌そうな態度なので、あえて話しかけないようにしている
・親側としては十分に話せていると思っていた
子どもが普段親の言葉を突っぱねてしまっていても実は寂しさの裏返しだったり、不安で悩んでいることもあります。



親にはできることなら本音で話したいし、辛いときには寄り添ってほしいと思ってるのね。
家庭が居場所であることを子どもは求めています。
ですので、親としてできることは、特に見返りは期待せず、話かけて会話が返ってきたらラッキー、
何かいい返事がなくてもOKという感覚で、日常での語り掛け・対話を促すことです。



言葉では「大丈夫だよ・楽にしていいよ」と言うものの内心辛く、態度と表情の不一致で子どもに違和感を与えてしまうことも少なくありません。
後で詳しく解説しますが、親御さんの心の持ちようも影響してきてしまうという点が注意です。
傾向④人の目が気になる
これまでに頑張って努力されてきた親御さんに多いのが、無意識のうちに世間の目が気になるという所です。



人の目を気にして比べてもどうにもならないことはわかっているし、子どもをそういった社会の基準で判断しては良くない
このように考えてはいるものの、そうなってしまうという方もいます。
これまで懸命に勉強して進学・就職と乗り越えてきた方の中には、これくらいできて当然と考える元の基準値が高くなっている方もいます。



周りと比較して子どもの出来具合も減点方式で見てしまうことに悩まれている方もいます。
子育て・不登校に対しても、周りの価値観や世間体を気にしてしまうことから、



しっかりした家庭でないと!きっちりしつけて学校に行かせないと
こういった思いが強く、何かあっても周りに相談できない部分があります。
しかし、子育て・教育に関しても絶対の正解はありません。世間の尺度からものを見ることを手放すと楽になるというメリットもあります。
不登校の子を持つ親が「疲れた」と思う3つの原因


疲れ①どのように対処してよいかわからない(状況が変わらない)
不登校の子どもをもつ親がつかれてしまう原因について深掘りしていきましょう。
保護者としても真剣に考えて行動しているからこそ、対処法がわからないともどかしく、身動きが取れなく苦しくなってしまって当然ですよね。
不登校に関して疲れる場面は例えばこのような場面があります。
・不登校の子どもに対する割合が夫婦間で異なる
・子どもがなんで不登校なのかずっと理解できない
・学校に行かせた方がいいのか、置いておいた方がいいのか未知
・誰に相談したらいいのかわからない



ご自身が悩まれていることは他の親御さん達も同じような内容で悩まれていることが多いです。
逆にここに当てはまることがないからといって、うちだけが抱えていて、他の人には理解されない内容なんだと悲しくなる必要もありません。
「不登校を繰り返す子どもから離れたい。
家の事情とか、学校の不理解とか、先生の暴言とか、友達からの嫌がらせとか、嫌なことがあっても、嫌なことなんて生きてれば誰だってあるのに、すぐに学校に行かなくなる。」
このように考えて、モヤモヤしている親御さんも身近に多くいます。
長いこと子どもが学校に行けないと、このような感覚にもなってきてもおかしくありません。
疲れ②子どもの将来に不安を感じる
子どもの不登校が続いている場合、将来に纏わることも不安になってくるかと思います。
不登校で子どもがずっと学校に行けない状態だと、このまま卒業できるのか、無事進学できるのか考えることがたくさんありますよね。
不安要素の例
- 学校に行かずに進学・就職できるのか
- 昼夜逆転でひきこもりの生活が続くのではないか
- 卒業に出席日数が足りるのか
- 全日制高校に進学できるのか



不安要素が多すぎるとどこから手をつけるか、子どもに何を言えばいいかも難しいの。



その中でも特に何が不安かが特定できていないと、解決策を脳内でずっと考えている状態になるので、より一層疲れてしまいます。
ですので、一度親御さん自身が不安に思ってる点はどこなのか、携帯や紙に書いて整理することをお勧めします。
疲れの要因として、漠然と子どもの将来が…と悩むよりも、不安点を明確化することで1ミリでも疲れを解消できるステップに近づけてみてほしいです。
不登校の過ごし方に関連するお悩みについてはこちらの記事でもまとめています。
例えば、昼夜逆転で施しようがないと思って放っておくと挽回がどんどん難しくなるのでその対処法も紹介しています。
▼ こちらもチェック ▼
不登校ともはやセットにもなっている昼夜逆転問題にはどう関わるかが重要です。
疲れ③不登校になった原因が親にあると責められた
これは言われると辛いものがありますが、「子どもの不登校が親の責任だ」ということを言われる場面もありませんか?
虐待やネグレクト・家庭環境の悪化に心当たりがあるのならまた話は変わってきますが、基本的に親のせいで不登校になるという直接的な因果関係はありません。



不登校は親が原因と言われることに関しても、そうじゃないかと考えることに関しても、考えれば考えるほど疲れた。
夫婦間で家事・育児と仕事を分担して行っている場合、最悪夫からも「母親の責任でしょう」と責められてしまうこともあります。



一生懸命子育てをしているというだけでも大変なのに、そのように追いつめられると行き場がなくなってしまって傷つきますよね。
心配しなくても大丈夫と言われても心配にはなるとは思います。



ですが子どもが不登校であるのは本当に自分のせいだと追い込まず、責めてくる言葉は真に受けないで大丈夫です。
不登校である子どもを育ていること自体がもう頑張っているので、否定されてしまったら疲れますよね。
親が疲れを抱え込まず、子どもが立ち直るための3つの行動


親が疲れに苛まれず、心身ともに健康な状態で不登校のお子さんに関わるにはどうしたらいいか学んでいきましょう。
家庭内を円満に保てると親御さんにとってもお子さんにとっても、生きやすくなります。
親は親で人生を楽しむ
親は親で自分のことをしましょう。
不登校で子どもが苦しんでいるからと、ずっとそばにいて対応してみて、果たして解決しましたか?
仕事での趣味でも、興味のあるジャンルの習い事など、自分の世界観をもつことで、子どもへの過度な干渉や心配ごとに使う時間を自分に充ててみてください。
登校拒否の子どもを心配するあまりにずっと家で付きっきりだと、親子共々ふさぎ込んでしまいます。



私がしっかりしないと!子どもの面倒をよく見ないと



こう張り切って、子どもが苦しんでるのに私は楽しんではいけないと、自分がしたいことに対して蓋をしてしまうんですよね。
しかし、子どもの立場からすると親が悩んで不安そうな表情で毎日過ごしていると、



無意識のうちに「自分の楽しんではいけない」「しんどそうにしていないといけない」という刷り込みが完了してしまいます。
それも意識的にそうしているのではなく、本人も気づかないうちなので、さらに苦しくなってしまいます。
人生を楽しんでいる親の姿は子どもに活力も与えます。言葉で働きかけるよりよっぽど効果的なのです。
家庭を離れるアイデア
- 趣味のサークルに入る
- 気心の知れた友人とごはんに行く
- 習い事をする
- カフェで読書する
これらは一例になります。はじめは少しだけ試してみるだけでも大丈夫です。
ご自身に合うものを探して取り組んでみてください。
固定観念に縛られずに受け入れる
みんなは普通に学校に行っているのだからうちの子もいけるはず、みんなは平気だからうちの子の大丈夫、と型にはめて考える癖がある場合、要注意です。



子どもからすると、気持ちを無視されたように感じて、親の話には耳を傾けてくれなくなってしまいます。
親は叱咤激励のつもりで言っていても、もうすでに限界まで頑張っている時にダメ出しをされたり、
固定観念で話されると、子どもは見放された気持ちになります。



自分のこと何も理解する気がないんだな
話を聞いてもわかってくれない、固定観念にとらわれた意見を押し付けてくるとなると、子どもはわざわざ親に話すことをやめます。
また、学校の先生が言う「学校に慣れるのには時間がかかる子もいます」や、「一時的なものですよ」といった一般論もお子さんに当てはまるものかはわかりません。



鵜吞みにせずに、一つ一つの周りの価値観に左右されずに、子どもの様子に合わせて受け入れるようにしましょう。
不登校から無理やり学校に行かせて、親子関係が悪化する道を辿るより、受け入れて子どもとの信頼関係を築くことが重要です。
第三者に頼る
子どもの不登校についての悩み、親御さん自身の悩みは早い段階で第三者を介して話すことをおすすめします。
やはり家庭内だけだと円滑に話し合いができなかったり、行き詰ってしまう場面も出てきます。
このようなやり取りはありませんでしたか?
母:なにしてるのー?お母さんもそのYouTube気になるなぁ(子どもとの対話が大事って聞いたし)
子:うるさい、放っておいて。
母:…。ねぇねぇ、〇〇の好きなプリン買ってきたよ。学校のことも決めようよ。
子:なんにもわかってないな。
不登校でゲームや動画三昧になっている状態で、はじめから円滑に会話できることを期待して話すと落ち込んでしまいます。



根気強く関わり続けることと、それだけだと親御さんも疲れてしまうので、第三者を挟むことで子どもの会話を引き出しやすくしましょう。
カウンセラーや専門家の方と話すことによって、客観的な視点からの意見が得られたり、過去の事例から適切な対応を助言してもらえるというメリットがあります。
また、親御さん自身が不登校の子どもに気を遣って我慢し続けていると、言葉と口調や表情の不一致がお子さんに伝わり、結果としてすれ違ってしまうケースもあります。
積極的に自分に合う第三者を探して、些細な事から相談できる先を作っておきましょう。
不登校がどんどんひどくなる…立ち直るきっかけは? まとめ


ここまで不登校がどんどんひどくなるケースや対処法、それに対して親御さんがしんどくなってしまう原因や対策を見てきました。
効果のある対処法を知らないと、親子共々消耗してしまいますので、そうなる前に記事で一緒に確認していきましょう。
この記事のまとめ
- 不登校は親の育て方が直接的な原因ではないことが多い
- 不登校の子どもに親の全部の時間を捧げるよりも、親は親で自分の時間をとって楽しむ
- 固定観念に縛られず、子どもの意見を尊重し受け入れる